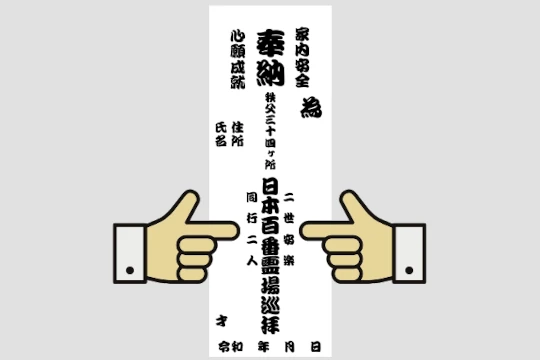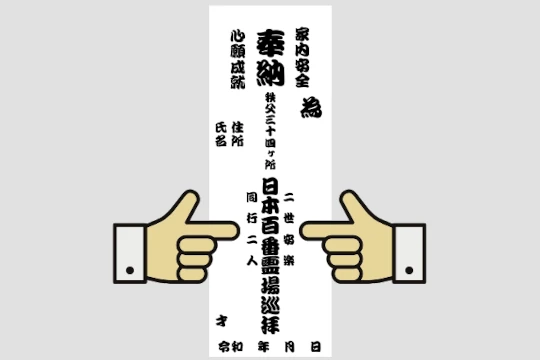
秩父札所とはどのようなものか?信仰の対象や【札】を解説!
- 公開日:
秩父観音霊場・札所めぐりで使うGPS対応巡礼地図を作りました。


秩父札所の観音さまは、1番四萬部寺の聖観世音菩薩から始まり、34番水潜寺の千手観世音菩薩まで、各札所で御本尊は異なり、その他には、十一面観世音菩薩、准胝観世音菩薩、如意輪観世音菩薩、馬頭観世音菩薩と、前述の観音さまも含めて全部で6観音が祀られています。
古くは奈良から平安時代に登場した高僧、行基、慈覚大師、恵心僧都などにより、お告げや祈祷の法力をもって彫刻され、生み出された仏像が、各札所の象徴となっていったわけですね。
ではなぜ、いろいろな姿の観音さまがいるのでしょうか。それは、観音経というお経の中にすべて答えがあります。

観音さまと聞くと優しい顔立ちで、美しく中性的なイメージを持たれるかもしれません。しかし、観音経(妙法蓮華経観世音菩薩普門品第二十五)によれば、観音さまは、三十三の姿(仏・辟支仏・声聞・梵王・帝釈・自在天・大自在天・天大将軍・毘沙門・小王・長者・居士・宰官・婆羅門・比丘・比丘尼・優婆塞・優婆夷・長者婦女・居士婦女・宰官婦女・婆羅門婦女・童男・童女・天・龍・夜叉・乾闥婆・阿修羅・迦楼羅・緊那羅・摩睺羅伽・執金剛神)に形を変えて、迷いを持つ人のところに現れて法を説くとあります。言いかえれば、観音さまの美しい中性的イメージも、変幻自在に変えたお姿の一つでしかなく、観音さまは仏にも夜叉にもなって、すべての人々を救済するということです。

ちなみに、京都の三十三間堂もそうですが、西国三十三所巡礼や坂東三十三観音の【33】は観音経のこの部分(観音さまの三十三変化)が由来になっています。
現実社会において、右隣は光り輝く柔和な顔立ちの仏様のような優しい人、左隣は自分の利益しか考えず、他者を踏み台にする夜叉のようなヒステリックな人。そんな状況は誰もが理解できると思います。でもそれは、ひょっとしたら観音さまの化身なのかもしれないということなんですね。こういう人間になりなさい。絶対にこうなってはいけませんよ。と、身をもって大事なことを示されると、観音経では伝えています。
要するに、観音さまは無限に変化するということです。ひょっとしたら、あなたの隣りにいる人も観音さまかもしれません。このような理由から、秩父札所の六観音も、いろいろな姿をしているわけですね。
観音経の冒頭の部分です。
聞是觀世音菩薩。一心稱名。觀世音菩薩。即時觀其音聲。皆得解脱。
ここがとっても大事なところで、苦しい時に観音さまの話を聞き、一心に名前をとなえれば解放されるということが書かれています。具体的には、【南無観世音菩薩】これだけです。南無観世音菩薩!南無観世音菩薩!南無観世音菩薩!と心を込めて唱えるだけで、問題は全て解決すると観音経にはあるんですね。

南無観世音菩薩! 南無観世音菩薩!
ほとんどの人がそんなの嘘だ、迷信だと考えるでしょう。ただし、それは無知で未熟なだけかもしれません。自分の中の夜叉も、他人の中の夜叉も全て認めて、自分を赦すことから始まります。そして、自分の無知や未熟さを知り、【南無観世音菩薩】と一心に唱えれば、恐れるものなど何一つ無くなり、問題も解決してしまうという世界観。あなたは信じますか?